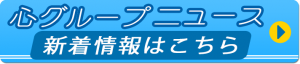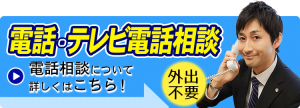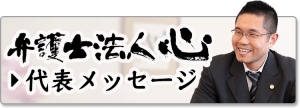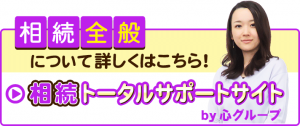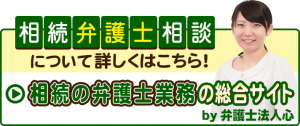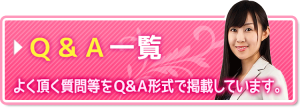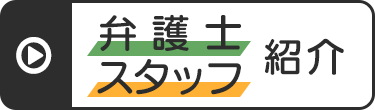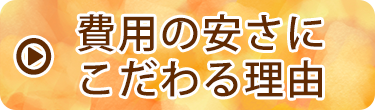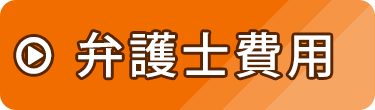未成年者の相続放棄|親権者が代理する際に注意すべき利益相反
相続では、借金などの負債を含めた遺産を被相続人から承継することになり、未成年であろうと、その負債を負ってしまうことになります。
借金などの負債がプラスの財産を超える場合に検討すべき方法の一つが、「相続放棄」です。
未成年者であっても相続放棄をすることはできますが、未成年者であるための制限があります。そこで、注意すべきは「利益相反」の問題です。
今回の記事では、「未成年者の相続放棄」に焦点を当てて、特に「利益相反」について詳しく説明します。
1 未成年者の相続放棄
相続放棄は「法律行為」ですので、未成年者が単独で行うことはできません。
未成年者が相続放棄を行う場合は、未成年者に代わって、法定代理人がその未成年者の相続放棄を行うことになります。
通常は、親権者である親が代理人となって、その子の相続放棄を行います。
両親の死亡などで親権者がいない場合は、未成年後見人が代理人となって相続放棄を行うことになります(民法838条1号)。
2 未成年者の相続放棄と利益相反
親が未成年者の代理人として相続放棄を行う場合、「利益相反」が問題となることがあります。
親と未成年の子供が利益相反の関係にある場合には、親がその子供の代理人になることはできず、特別代理人を選任する必要があります(民法826条)。
ここでは、この「利益相反」について、詳細に見ていきます。
⑴ 利益相反の場合に特別代理人が必要な理由
利益相反とは、読んで字の如く「当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと」をいいます。
民法第826条に、次のように定められています。
民法第826条
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
⑵ 親権者と未成年者が利益相反となるケース
例えば、次の例を見てみましょう。
被相続人:夫
相続人:妻、未成年の子供1人
この事例では、配偶者である妻と子供がともに同じ被相続人の相続人となり、配偶者は子供の親権者でもあります。
この場合、子供が相続放棄を行うことで配偶者の法定相続分が増えますので、子供の意向を無視して配偶者が勝手に相続放棄を行うと、配偶者は利益を得て、子供の利益が失われてしまいます。
解決方法としては、次の2つの方法があります。
特別代理人の選任をする
親権者と子供が利益相反の関係にある場合には、民法において「特別代理人が必要」と定められています(民法828条1項)。
特別代理人とは、遺産相続が発生した際、その相続人が未成年の場合に、家庭裁判所によって特別に選任される代理人のことをいいます。
特別代理人を選任し、特別代理人が未成年の子供に代わって相続放棄を行います。
親権者が事前、あるいは子供と同時に相続放棄をする
親権者が相続放棄を行えば、その親権者は相続人ではなくなり、親権者と未成年の子供の利益相反は解消されます。
親権者が事前に自分の相続放棄を行うか、自分の相続放棄と未成年の子供の相続放棄を同時に行うことにより、親権者とその子供との利益相反状態はなくなるので、子供の代理人として相続放棄が可能となります。
3 利益相反が問題となる相続放棄の事例
では、ここから親と子供が利益相反となる相続放棄のケースを詳しく見ていきます。
⑴ 共同相続人である親権者が一部の子供の相続放棄を代理
被相続人:夫
相続人:配偶者である妻、子A、子B、子C(子供はすべて未成年者)
親権者:配偶者である妻
相続放棄をする相続人:子Aのみ
配偶者は、子Aの親権者であると同時に同じ被相続人の相続人となりますので、子Aと利益が相反することになり、子Aの代理人になることはできません。
また、子供3人全員に特別代理人の選任が必要となります。
親権者が事前または子Aと同時に相続放棄をすれば、少なくとも、親権者と子Aの利益が相反することがありません。
しかし、子供同士(子Aと子B・Cの間)の利害は相反するため、子B、子Cに特別代理人を選任することで、子Aについては代理人となることが可能です。
⑵ 共同相続人である親権者が子供全員の相続放棄を代理
被相続人:夫
相続人:配偶者である妻、子A、子B、子C(子供はすべて未成年者)
親権者:配偶者である妻
相続放棄をする相続人:未成年者の子供全員
このケースでも、親権者と子供全員の利益が相反する関係となるため、子供3人全員に特別代理人の選任が必要となります。
しかし、この場合には、親権者が事前または子供と同時に相続放棄をすれば、子供全員が相続放棄をしても、利益が相反することにはならず、子供全員を代理して相続放棄をすることが可能です。
⑶ 共同相続人とならない親権者が一部の未成年者の相続放棄を代理
次に、夫がすでに亡くなっているため、夫の父親を複数の未成年の子供が代襲相続し、親権者である妻がその一部を代理するケースを考えてみます。
被相続人:夫の父親
相続人:子A、子B、子C(子供はすべて未成年者)
親権者:既に亡くなっている夫の配偶者である妻
相続放棄をする相続人:子Aのみ
この場合、未成年の子供同士の利害は相反しますが、母親は夫の父親の相続人とはならないため、子と母親の利害は相反しません。
したがってこのケースでは、子A以外の子供に特別代理人を選任することで、配偶者が子Aを代理することができます。
⑷ 共同相続人とならない親権者が子供全員の相続放棄を代理
次のケースも、父親がすでに亡くなっているため子供が代襲相続する場合です。この場合には、代襲相続人となる未成年の子供全員が相続放棄をします。
被相続人:夫の父親
相続人:子A、子B、子C(子供はすべて未成年者)
親権者:既に亡くなっている夫の配偶者である妻
相続放棄をする相続人:未成年者の子供全員
このケースでも、親権者が事前または子共と同時に相続放棄した場合と同様に、子供全員の相続放棄について親権者が代理することは、利害相反となりません。
親権者が子供全員の代理をすることができ、特別代理人の選任は必要ありません。
4 未成年者の親権者が離婚している場合
両親が離婚している場合でも、その子供は、父親と母親の両方の相続権を持っています。
ここでは、両親が離婚している場合に焦点を当てて、未成年の子供の相続放棄について見ていきます。
⑴ 親権者でない親が亡くなった場合の相続放棄
最初に、離婚後、親権者とならなかった親が亡くなった場合の相続放棄について考えてみましょう。
相続人となる子が1人の場合
父親と母親が離婚後、母親が1人っ子である未成年の子Cの親権を取得した後に、父親が死亡した場合についてです。
被相続人:離婚した父親(子Cの親権者でない)
相続人:子C(未成年者)
親権者:母親
相続放棄をする相続人:子C
父親の相続については、子Cの親権者である母親は、父親と離婚しているため法定相続人とはならず(民法890条)、母親と子Cは利益相反の関係にありません。
そのため、特別代理人は不要で、母親が子Cの代理人として相続放棄が可能です。
相続人となる子が複数いる場合
次に、この夫婦に、複数の未成年の子供がいるケースについて考えてみます。
被相続人:離婚した父親(子Cと子Dの親権者でない)
相続人:子C、子D(子供はすべて未成年者)
親権者:母親
相続放棄をする相続人:子共全員
母親は、父親の相続人とはなりませんが、子Cと子D両方の親権者ですので、母親は、同時に子C・子D両方の代理人になることはできず、親権者である母親が代理する子を除き特別代理人の選任が必要となります。
例えば、母親が子Cを代理する場合には、子Dについては特別代理人の選任が必要となります。
⑵ 親権者の親が亡くなった場合の相続放棄
次に、離婚後親権者となった親が亡くなり、相続放棄をする場合についてです。
ちなみに、親権者が亡くなると、未成年者には親権者がいなくなってしまうため、離婚した元配偶者が、「親権者変更の申立」を行って、その未成年者の親権を取得します。
相続人となる子が1人の場合
離婚後、親権を取得し、子Cを育てている母親が亡くなりました。
被相続人:母親(子Cの親権者)
相続人:子C(未成年者)
親権者:母親
相続放棄をする相続人:子C
母親の死亡により子Cの親権を取得した父親は元妻の相続人とはなりませんので、父親が子Cの代理人となって相続放棄をすることができ、特別代理人の選任は不要です。
相続人となる子が複数いる場合
同じ元夫婦に未成年の子供が複数いる場合についてです。
被相続人:母親(子C、子Dの親権者)
相続人:子C、子D(子共はすべて未成年者)
親権者:母親
相続放棄をする相続人:子共全員
この場合は、父親が子Cと子D両方の親権者となりますが、母親Bの相続人とはならないため、親権者が代理する子を除き特別代理人が必要となります。
5 未成年者の相続放棄は弁護士にご相談を
今回は、「未成年者の相続放棄」、特に「利益相反」に焦点を当てて説明しました。
未成年者が相続放棄を行う場合は、通常、親権者が代理人になって相続放棄を行いますが、利益相反に該当する場合は「特別代理人」を選任しなければなりません。
特別代理人の選任や相続放棄の手続きは簡単ではなく、相続放棄ができる期間が3ヶ月間(民法915条1項)ということを考えると、それほど余裕はありません。ちなみに、未成年の子供が相続放棄できる期間は、代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となります。
未成年者の相続放棄をお考えの方、お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度お気軽にご相談ください。